令和7年分年末調整の改正ポイント
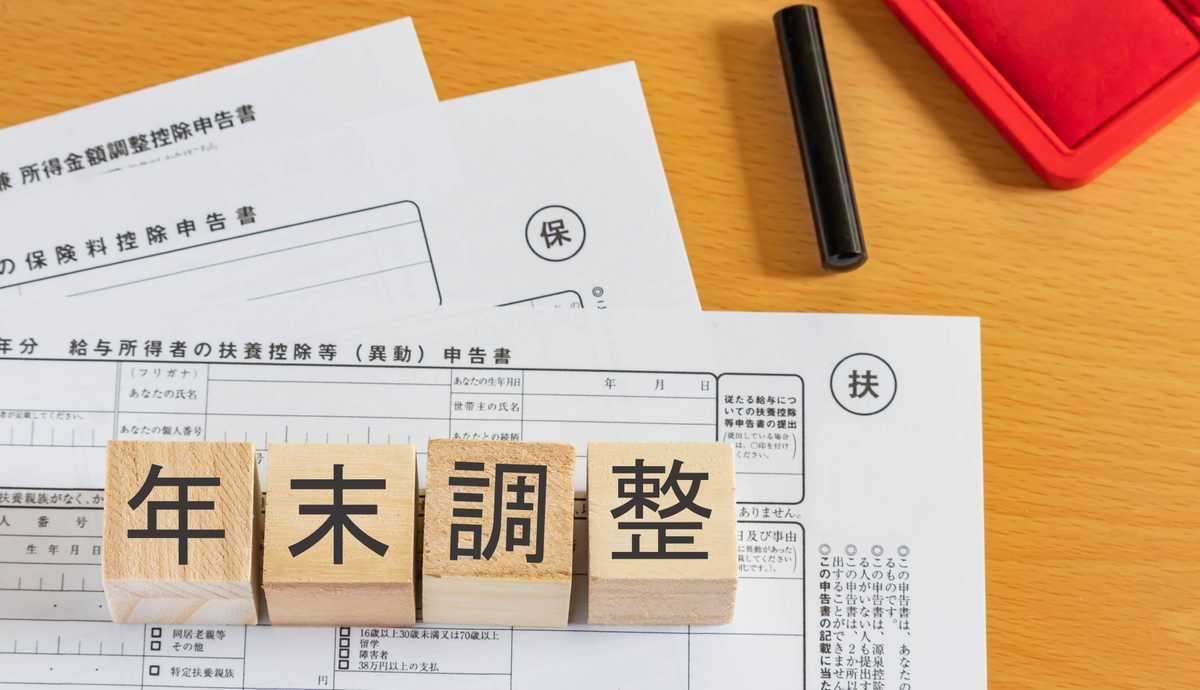
早くも年末調整の準備をする時期になってまいりました。
令和7年度の税制改正は、所得控除制度に大きな見直しが行われた年となりました。基礎控除や給与所得控除の引き上げ、そして「特定親族特別控除」の新設が主な改正内容です。これらの改正は単なる控除額の変更にとどまらず、年末調整の手続きや申告書様式にも影響を与える実務的なポイントを多く含んでいますので、ポイントを簡単にまとめてみます。
1.基礎控除の引上げと時限的上乗せ措置
まず、所得税の基礎控除額が一律10万円引き上げられ、標準額は58万円になりました。さらに、合計所得金額が655万円以下の居住者には、所得水準に応じて最大37万円の上乗せが行われます。上乗せ措置のうち、所得132万円以下の低所得層への上乗せは恒久的に続きますが、中間所得層(132万円超~655万円以下)への上乗せは令和7年分と8年分の2年間に限られた時限措置となります。
この背景には、物価上昇に比べて賃金上昇が追いつかない現状への配慮があります。与党提案による修正では「中所得者層を含めた税負担軽減」が明確に掲げられ、消費を支える層を一時的に支援する狙いが示されました。
この改正は令和7年12月1日に施行され、同年の年末調整から適用されます。そのため、11月までの源泉徴収では旧基準が使われ、年末にまとめて精算する形となりますので、事務担当者の負担増が考えられます。
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ
次に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これは令和2年改正で一度引き下げられた部分を元に戻すもので、最低賃金の上昇やインフレの進行を踏まえた見直しです。
これまでの制度では、一定以下の収入層は控除額が固定化され、収入が増えても控除が増えない仕組みになっていました。今回の改正は、物価上昇に対応するとともに、「働き損」といわれる就業調整の弊害を緩和する目的があります。この改正も年末調整で反映され、年間の源泉徴収税額との精算で調整されます。
3.特定親族特別控除の創設
新たに創設された「特定親族特別控除」は、教育や生活支援の観点から、若年層を抱える家庭を支援する制度です。対象となるのは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(または里子)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方です。控除対象扶養親族に該当しない若年層を支援する新しい仕組みといえます。
控除額は所得に応じて段階的に設定され、最大で63万円が控除されます。適用を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
なお、この制度は既存の「特定扶養親族に係る扶養控除」と似ていますが、目的が異なります。特定扶養控除は教育費負担の軽減を目的として導入されたのに対し、特定親族特別控除は「扶養控除を受けられない層」に対する緩和措置です。大学生などがアルバイトで一定の所得を得た場合でも、世帯の負担を軽減できる仕組みとなっています。
今回の改正は、単なる税率や金額の見直しにとどまらず、「生活防衛」「所得再分配」「若年層支援」といったメッセージを含んでいるようにも感じます。中間所得層や子育て世帯を意識した構成は、家計のセーフティネットとしての役割を果たそうとしているようにも見えますので、年末が明るくなることに期待です。
公的保険アドバイザー協会
理事 福島紀夫
